皆さん、こんにちは。
神奈川県川崎市を拠点に、土木工事・舗装工事・上下水道管工事などを手掛けている加藤土建株式会社です。
現在、建設業界は「2024年問題」に直面しています。これは簡単にいうと「働き方改革を目的とする法改正に対応しなければならない」というものです。
労働者にとっては基本的にメリットですが、企業は労働環境の大幅な見直しをしなければなりません。建設業界で働く方も、2024年から何が起きるのかを知っておくことが大切です.
ここでは、建設業における2024年問題の内容や背景、企業に求められる対応について解説します、
採用情報はこちら⇒https://recruit.careecon.jp/co/kato-doken/jobs
■建設業における2024年問題とは?

2024年問題とは、いわゆる「働き方改革関連法(関連する8つの法改正の総称)」による規制が、2024年4月から建設業界にも適用されることです。具体的には、労働時間の上限規制が罰則付きで設けられることを指します。
働き方改革関連法は、日本の労働環境改善や生産性向上、公正な待遇の確保、多様な働き方の実現などを目的として、2018年に成立しました。労働時間の上限規制は、その中でも特に重要なポイントの1つです。2019年4月1日から順次施行され、大企業では同日から、中小企業では2020年4月1日から適用されています。
しかし、建設業では長時間労働が状態化しており、すぐに対応できる状態ではありませんでした。そのため、特例として5年間の猶予期間が設けられたのです。建設業界以外では、ドライバー職や医師などにも猶予期間が設けられています。
そして、2024年4月からは、いよいよ建設業にも働き方改革関連法が適用され、労働時間の上限規制が設けられます。しかも罰則付きで、違反した事業者には6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、守らないわけにはいきません。
では、具体的にどのような基準が設けられるのでしょうか? まず労働基準法では、労働者の実労働時間を8時間/日、40時間/週と定めています(法定労働時間)。また、いわゆる36(サブロク)協定を労使間で結んでいる場合は、45時間/月および360時間/年を上限とする時間外労働(残業)が可能です。
法改正の前は、ここからさらに「特別条項付き36協定」を結んでいると、残業時間の上限が実質的になくなり、労働者を際限なく働かせることができるという問題が生じていました。しかし、働き方改革関連法が適用されると、特別条項付き36協定でも上回ることができない上限規制が設けられます。
具体的には、時間外労働(休日労働を含む)が720時間/年まで、同じく100時間未満/月まで、2ヶ月~6ヶ月の時間外労働の合計が80時間/月まで、時間外労働45時間を超過できる月が年6回までとなっています。現状すでにこの基準を上回っている会社は、2024年4月までに改善しなければなりません。この状況を2024年問題と呼んでいるわけです。
■建設業界に働き方改革が求められる理由
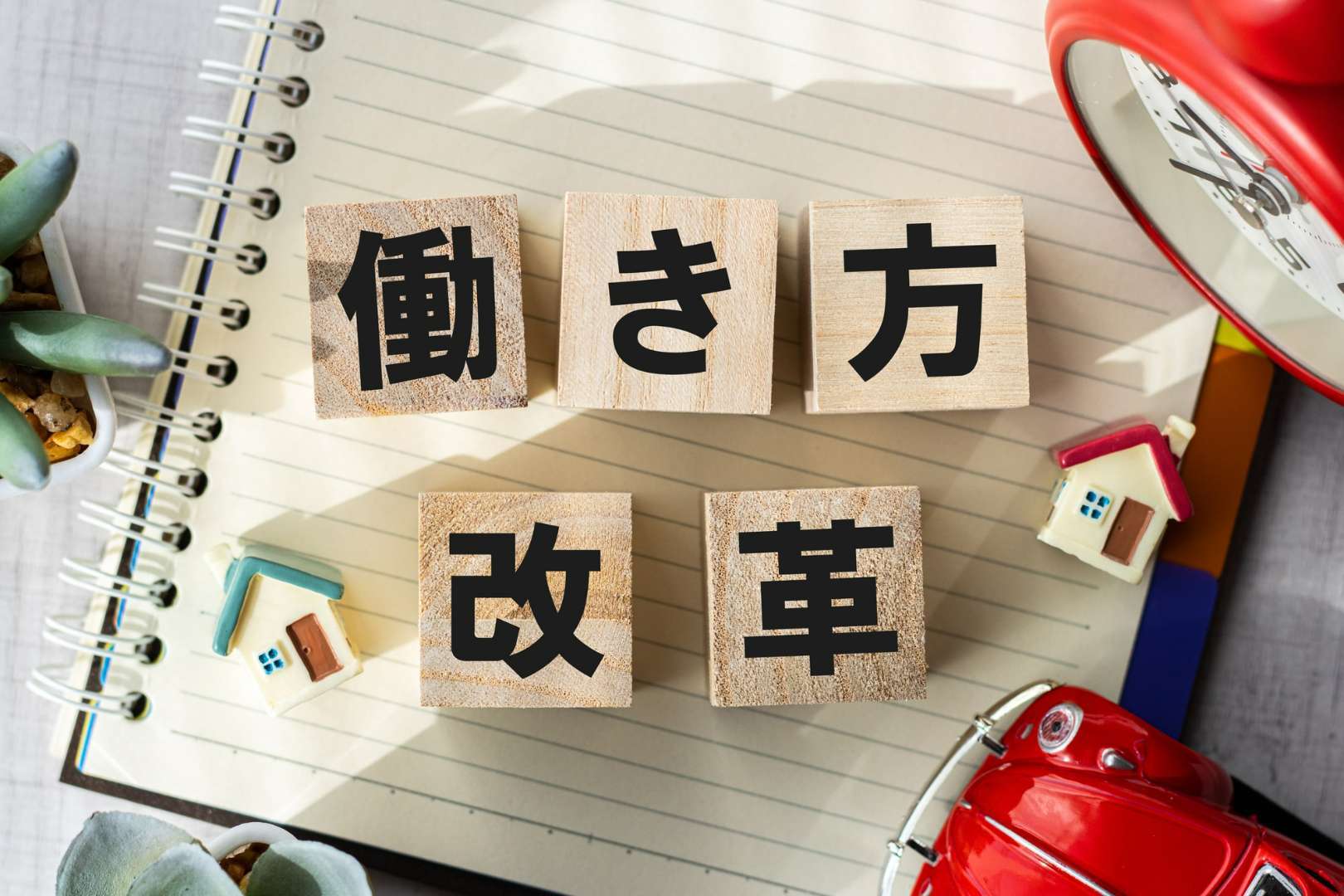
働き方改革は、あらゆる企業が実現しなければならない課題です。特に建設業界では、他の業界以上に働き方改革が求められています。
なぜなら、働き方改革法案の適用に猶予期間が設けられたことからもわかるように、建設業界は非常に多くの問題を抱えているからです。建設業界に働き方改革が求められる理由を見ていきましょう。
・深刻な人手不足
建設業界では人手不足が深刻化しています。2017年における建設業就業者数は約498万人で、ピーク時の1997年から約27%も減少しました。2025年には、最大90万人程度も労働人口が不足する見込みです。このままでは、建物や公共インフラの工事現場を回すことができず、社会の維持に支障をきたすかもしれません。
これほどまでに人手不足が進行しているのは、求人に対して就業者の数が足りておらず、定着率も低い(離職率が高い)からです。その原因については、以下の項目で詳しく解説します。
・長時間労働の常態化
建設業界では、ずっと以前から長時間労働が常態化しています。2021年度の統計によると、産業全体の年間実労働時間は1,632時間、年間出勤日数は212日でした。一方、建設業の年間実労働時間は1,978時間、年間出勤日数は242日となっています。つまり、建設業は他の産業に比べて、1ヶ月間も多く働いているのです。
このような状態のため、求職者からは敬遠されてしまい、求人募集をかけても思うように人が集まりません。また、せっかく就職してくれた人も、長時間労働に耐えかねて離職してしまうケースが多いのが実情です。そして、人手不足なので長時間労働になり、長時間労働だから人がやめるという悪循環に陥っています。
長時間労働になりやすい原因としては、下請けに負担が行きがちな多重請負構造や、工期を守らなければならないこと、非効率な働き方などが挙げられます。長時間労働を改善するためには、こういった業界の根本的な部分から見直しが必要なのです。
・少子高齢化による若手不足
少子高齢化によって若い労働者が不足していることも、建設業界の大きな問題です。少子高齢化は日本全体で問題になっていますが、建設業では他の業界以上に高齢化が進行しています。建設業就業者の年齢構成は、2022年の時点で55歳以上が約36%、29歳以下が約12%となっており、他の業界に比べて高齢化が著しい状態です。
ここまで若手から避けられてしまっているのは、やはり長時間労働を始めとする労働環境の悪さが原因だと考えられます。後継者不足に悩んでいる企業も多く、このままでは日本の優れた技術が継承できなくなってしまうでしょう。もちろん、人手不足の一因でもあります。今後の建設業界は、若者が希望を持てる業界を目指さなければならないのです。
■2024年の働き方改革に向け、企業が取り組むべき課題

この記事の掲載時点で、2024年4月までは約半年です。建設業界の企業は、働き方改革関連法案への対応を急がなければなりません。そのために企業が取り組むべき課題としては、以下のものが挙げられます。
・DXの推進
労働時間の上限規制に対応しようとして、単純に一人あたりの労働時間を減らすと、業務に支障をきたす可能性があります。働き方改革を実現するためには、ただ人を削るのではなく、効率のいい働き方へと転換しなければなりません。その手段として推進されているのがDX(デジタルトランスフォーメーション)です。
DXとは、さまざまなIT技術を活用して、ビジネスのあり方を見直すことをいいます。建設業界におけるDXの例としては、リモートワークやドローンによる測量、ICT(情報通信技術)による建機の自動化・遠隔操作、計画段階からの3次元モデルの活用(BIM/CIM)、クラウドサービスを活用した情報共有、AIによる画像・映像分析などが挙げられます。
建設業のDX化が進めば、業務の大幅な効率化が図られ、生産性がアップするでしょう。これは長時間労働の是正や、人手不足の解決にもつながります。また、働きやすい職場になるため、定着率のアップも期待できます。2024年問題に対応するためには必要不可欠です。
・「新3K」の推進による労働環境の改善
建設業界は、「きつい」「汚い」「危険」の3つがそろった「3K」業種だといわれてきました。実際そのような環境なのは否定できないところがあり、求職者から敬遠される理由にもなっています。今後は労働環境を改善して3Kから脱却するとともに、世間が抱くマイナスイメージを変えていく必要があります。
そこで重要になるのが「新3K」です。新3Kとは、3Kに代わるものとして国土交通省と日本経団連が提唱したキーワードで、「給与」「休暇」「希望」の3つを指します。能力に見合った給与が受け取れ、十分な休暇が取得でき、将来に希望が持てる業界にしていこうという試みです。これからは、新3Kを実現できているかどうかが、企業の評価のポイントになるでしょう。
新3Kについては以下の記事もご覧ください。
https://www.kato-doken.jp/blog/column/159763
2024年問題は、建設業界にとって避けては通れない問題です。これまで通りの長時間労働を続けたままでは、違法になってしまう企業も少なくありません。かといって、ただ労働時間や人員を削減すればいいわけではなく、企業は難しい対応を迫られています。
そのため、今から建設業界に就職する場合は、2024年問題にうまく対応している企業を選ぶことが重要です。建設DXや新3Kを推進し、労働環境を整えている企業であれば、安定して働くことができます。まずは、企業の情報をしっかりとリサーチしましょう。
加藤土建では新3Kを推進し、建設業の働き方改革に貢献しております。完全週休2日制を実現している弊社は土日祝日が休みで、年間休日は120日以上取得可能です。賞与は1年で最大3回支給(賞与2回+決算賞与)し、未経験者であっても入社1年目から年収400万円以上をお約束しています。
働きやすい環境を整えた結果、離職率は非常に低く、どの従業員も仕事とプライベートを両立させながら働けるようになりました。資格取得支援制度をはじめとする福利厚生も充実し、県外への長距離移動もほぼないため、未経験者でも安心です。新3Kの職場で快適に働きスキルアップしたい方は、ぜひお気軽にご連絡ください。皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしております。
https://recruit.careecon.jp/co/kato-doken
関連記事
建設業の週休2日制はいつから?2024年4月から始まる義務化の影響と課題を解説
建設業界の年間休日日数は全国平均と比較して少ない?その理由や、業界の取り組みを解説
仕事の「新3K」とは?│建設業界₌3K労働は古い!イメージを覆す業界の最新動向を紹介
若者が建設業から離れるのはなぜ?当たり前と思われるその理由と対策について解説!
建設業がSDGsに取り組む必要性は?建設業界におけるSDGsの取組事例をご紹介!


